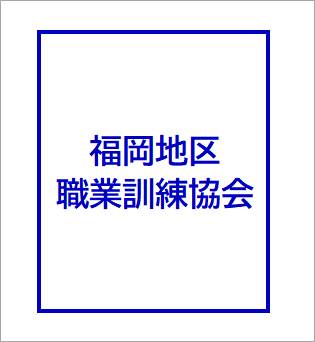【福岡女学院大学】特別講座:教養・万葉の歌と心 第1講・第2講
福岡
福岡県全域
文化・芸術・スポーツ
教育
リカレント教育(学び直し)
| 開催日時 | 2025年5月14日 13時30分 ~ 7月9日 15時00分 |
|---|---|
| 開催場所 | 福岡女学院大学 エリザベス·リー ホール(福岡市南区曰佐3丁目42−1) |
| アクセス | 西鉄天神大牟田線 井尻駅から西鉄バス45番に乗車(約12分)・西鉄天神大牟田線 大橋駅から西鉄バス42番に乗車(約13分)・鹿児島本線 南福岡駅から西鉄バス45番に乗車(約15分) |
| 参加費 | 各講 受講料 2,000円 + 教材費 100円 ずつ |
| 定員 | 100名 |
| 主催者 | 福岡女学院大学 地域・国際交流センター(生涯学習) |
| お問い合わせ | 福岡女学院大学 地域・国際交流センター(生涯学習) TEL: 092-575-2993 Email: shogai@fukujo.ac.jp |
| 特記事項 | 事務手数料500円(1回のお申込みにつき・複数講座申込可)が別途必要となります。 ※【第1講】【第2講】の1日だけの受講もお選びいただけます。1日だけ受講される場合は講座申込フォームの備考欄に希望の日程をご記入ください。 |
内容
【第1講:5月14日】 歓びの歌―志貴皇子の息吹き―
白鳳万葉時代に生きた志貴皇子の「石走る垂水の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも」(巻8・一四一八)の歌を読んでみましょう。ご覧のように上句では助詞「の」を畳みこみ、下句では「さわらびの」以下、一気にうたい結ぶ力強さがあります。うたわれるのは春の躍動そのもので、たしかに「秀歌」というべきでしょう。ところで、この志貴皇子の感性が、はるかユーラシア大陸の西の端、北欧古代の人びとのそれと、しっかりつながっているといえば、いささか強弁に過ぎるでしょうか。志貴皇子の生涯にもふれながら、万葉の歌と心を明らかにしたいと思います。
【第2講:7月9日】 清冽な水辺で―大伴旅人の松浦遊覧の歌―
天平時代初期、大宰帥(鎮西大宰府の長官)だった大伴旅人は、肥前国松浦郡(現在の佐賀県唐津市周辺)に小旅行をしています。その折の作である「松浦川に遊ぶ序」とそれに続く「松浦なる玉島川に鮎釣ると立たせる児らが家道知らずも」(巻5・八五六)ほかの連作を鑑賞します。どうやら旅人は、現地ルポとしてこれらの歌をうたったわけではなさそうです。あわせて『文選』をはじめとする海彼の作品も視野に入れて、当時の文人たちの間で流行っていた「河洛神女」の文学も味わいましょう。
講師:東 茂美/福岡女学院大学 名誉教授・文学博士
※【第3講】10月8日、【第4講】12月10日につきましては、受付が9月頃となります。